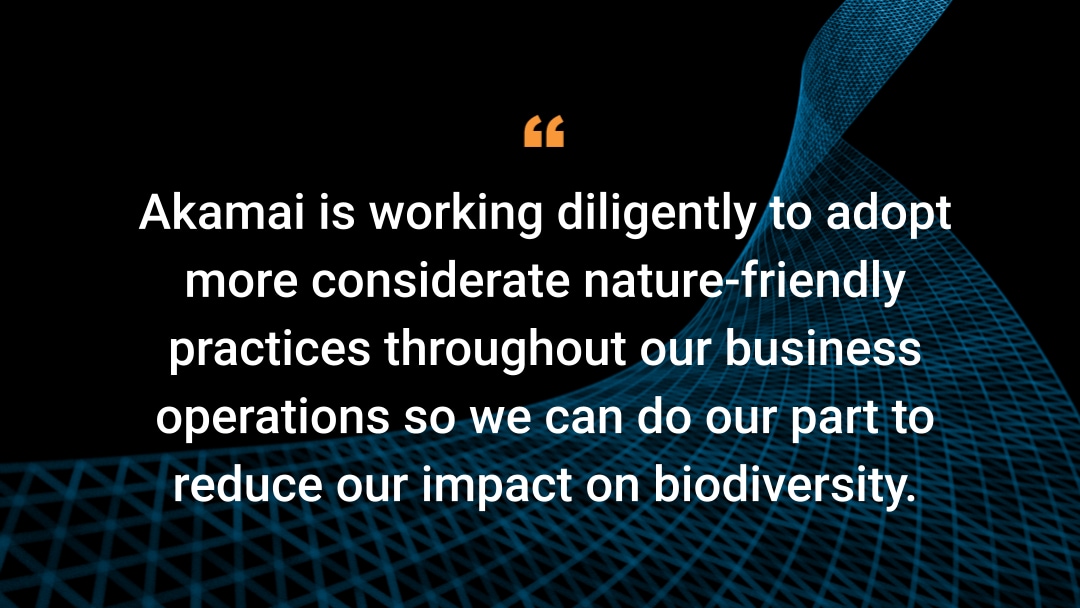地域ごとの特色あるサステナビリティプログラム
Akamai の Director of Corporate Sustainability 兼 ESG Officer である Mike Mattera と筆者がサステナビリティに関する意見交換ツアーを本格的に開始してから 1年が経ちました。2024 年には、欧州・中東・アフリカ(EMEA)地域の Akamai のお客様や従業員と対談し、こうした主要なステークホルダーがサステナビリティについてどのように考えているのかを把握し始めました。
この地域から対話を始めた理由は、規制フレームワークが発展しており、エンゲージメントの水準が高かったからです。私たちは、何がうまくいったのか、何が困難なのか、どこで行き詰まっているのかを知り、それに合わせたサポートを行えるようにしたいと考えていました。
徹底的な調査と話し合いの後、フィードバックを活用して 2 つの学習モジュールを作成しました。この学習モジュールは、お客様が抱えている上記のようなギャップを Akamai の従業員が埋められるようにするために、営業リーダーと協力して開発されました。膨大な労力を費やしましたが、直接的なフィードバックループを確立して、Akamai のプログラムを形成する機会をお客様に提供する上で、重要なステップでした。
この最初の話し合いを行った後、私たちはこの取り組みの対象を拡大し始めました。サステナビリティに画一的なアプローチが存在しないことは、常に認識していました。そして、世界の他の地域ではサステナビリティにどのような意味があるのかを考える時がきたのです。EMEA で機能するものが、他の地域では機能しない場合があります。その逆もまた然りです。
このような土台が整ったため、今年はアジア太平洋(APAC)地域で引き続き対話を行い、東京、シンガポール、シドニーの主要なステークホルダーを訪問して、地域ごとの違いを Akamai のプログラムに取り入れることにしました。
さまざまなステークホルダーと対話しました
お客様、従業員、パートナー、同業他社、競合企業、アナリスト、報道関係者、再生可能エネルギー開発者など、幅広いステークホルダーグループと関わりを持ちました。このようなグループと交流したことで、状況を俯瞰し、より大局的な視点でとらえることができました。
一部のお客様は APAC で再生可能エネルギーを調達しようとしていますが、それはこの地域では特に困難である可能性があります。また、新事業の一環で、二酸化炭素排出量を測定しようとしているお客様もいらっしゃいます。サステナビリティの取り組みにおいて、どの段階にあるかはお客様ごとに異なりますが、だからこそ、Akamai ができることに関する貴重な見解を得ることができました。
また、Akamai の従業員とも深い話し合いをすることができました。対話の内容は国によって異なりますが、Akamai の 2030 年の目標に関する詳細な質問を数多く受けました。たとえば、プラットフォームと事業運営に 100% 再生可能エネルギーを使用し、排出量ネットゼロを達成することなどです。
Akamai の従業員はこれらの戦略を深く掘り下げるだけでなく、業界においてその戦略にどのような独自性があるのかについて詳しく知りたいと考えていました。また、Akamai の従業員からは、サステナビリティに関する Akamai のコミットメントが本物であることをお客様に信じてもらうためにはどうすればよいかという質問も上がりました。そして、Akamai のミッションクリティカルな目標や事業におけるその他の重要な要素にサステナビリティが織り込まれていることを、お客様に自信を持って伝えることができると喜んでいました。
仮定を立証し、新たな知見を得ました
多くのリーダーと対話するほど、重要なテーマが浮かび上がってきました。
まず、APAC は画一的ではないという仮定が立証されました。お客様のニーズ、規制、インフラには、他の地域で見られた以上に、国による大きな差異があります。そのため、より多くの時間を費やして、まずは各市場の固有の状況を把握し、それに応じてアプローチを調整する必要があります。これは大変なことのように聞こえますが、プログラムを拡大し続ける中で多くの機会をもたらします。
また、この地域のお客様の関心と行動には信憑性があるというという仮定が立証されました。さらに、Akamai のその他の取り組みも共感を得られる可能性があることが分かりました。
たとえば、Akamai は多くの場合、ネットゼロ戦略や環境規制を入口として、ステークホルダーとの対話を始めます。これらは、他の地域の一定のオーディエンスにとっては非常に重要なテーマのようです。しかし、APAC では、これらのトピックは興味を引きますが、ネットワークの効率化による廃棄物削減の取り組みの方が共感を得られる場合があることが分かりました。
今後も対話できることを楽しみにしています
時間をかけて、この数週間で得たすべてのフィードバックを咀嚼することができたので、APAC における Akamai の戦略がさらにはっきりとしてきました。こうした対話は地域限定で実施しましたが、今こそサステナビリティのトピックについてお客様と関わりを持つべきであることは明らかです。逆風や複雑さが存在することは確かですが、適切なアプローチで取り組めば進展させることができます。
確かに、ステークホルダーとバーチャルで面談することもできました。しかし、時間をかけて対面して話すことで、Akamai のプログラムを方向づける直接的なフィードバックループを確立することに私たちが真剣に取り組んでいることを示すことができます。そして、私たちは長旅に見合った確かな成果を得ることができました。
その新しい知見を活用し、今後もサステナビリティに関する独自の取り組みを進めているお客様が抱えるギャップを埋めてまいります。また、他の地域でも対話を続けることを楽しみにしています。参加者が多いほど議論が深まり、Akamai のプログラムが強化されます。
地域特有のサステナビリティに関する独自の知見をお持ちのお客様は、ぜひ貴社担当アカウントチームにご連絡いただき、対話しましょう。